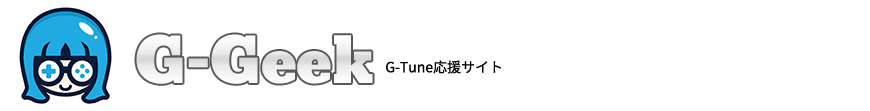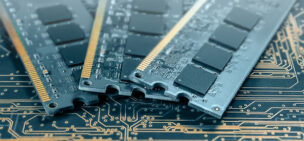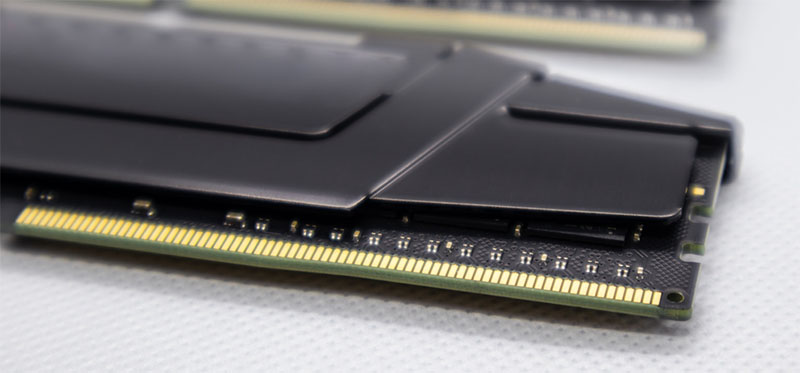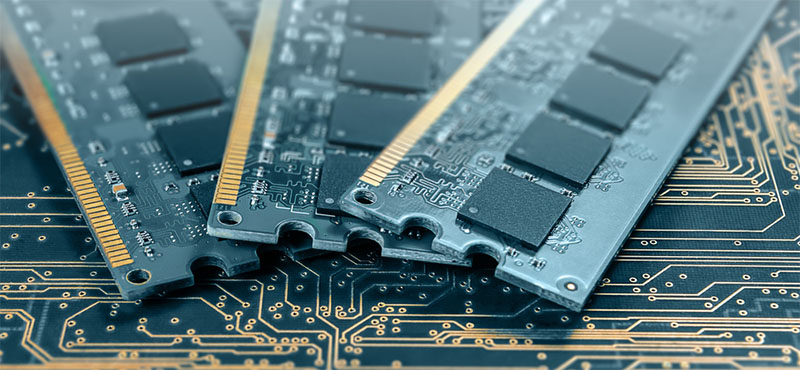
ゲーミングPCを組む際、「メモリの容量やクロック(MHz)」を重視する人は多いですが、「メモリのランク(Rank)」について考えたことはありますか?
実は、メモリのランク(Single Rank・Dual Rank・Quad Rank)は、ゲームのfpsや動作の安定性に影響を与える重要な要素です。
例えば、「同じ16GBのメモリでも、Single RankよりDual Rankの方がフレームレートが向上する」といったケースもあります。しかし、なぜランクの違いでパフォーマンスが変わるのでしょうか?
本記事では、「メモリのランクとは何か?」から、「ゲーミングPCに最適なメモリの選び方」までを詳しく解説します。
メモリのランクとは?
メモリの「ランク(Rank)」とは、1つのメモリモジュール(DIMM)内でデータのアクセス方式がどう構成されているかを示す概念です。
ランクが異なると、データの転送効率やメモリコントローラーの負荷が変わるため、パフォーマンスに影響を与えることがあります。
Single Rank(シングルランク)
・メモリチップが片側にのみ搭載されている(1グループ)
・一度にアクセスできるデータ量が少ないため、アクセス速度が安定しやすいが、帯域幅が低い
・低コスト・低発熱だが、パフォーマンスはDual Rankに劣る
Dual Rank(デュアルランク)
・メモリチップが両側に搭載されている(2グループ)
・一度にアクセスできるデータ量が多く、帯域幅が向上し、パフォーマンスが向上
・ただし、メモリコントローラーの負荷が増えるため、対応するマザーボードや設定が重要
Quad Rank(クアッドランク)
・1枚のメモリモジュールに4グループのメモリチップが搭載されている
・サーバーやワークステーション向けの構成が多く、高密度メモリを搭載可能
・メモリコントローラーの負担が大きくなり、ゲーミング用途ではあまり使われない
メモリのランクがゲームのfpsに与える影響
では、メモリのランクによって、ゲームのフレームレート(fps)にどれほどの違いが生じるのでしょうか?
実際のベンチマークデータをもとに、Single RankとDual Rankの違いを検証してみます。
検証環境
CPU:Ryzen 7 7800X3D
GPU:RTX 4070 Ti
メモリ:DDR5-6000 CL30(Single Rank / Dual Rankの違いのみ比較)
ゲーム:Cyberpunk 2077、Apex Legends、Hogwarts Legacy
ゲーム別 fps比較(平均値)
ゲームタイトル、Single Rank、Dual Rank、差
Cyberpunk 2077(1440p, RT ON)、72 FPS、80 FPS、+11.1%
Apex Legends(1080p, 高設定)、225 FPS、245 FPS、+8.9%
Hogwarts Legacy(1440p, 高設定)、78 FPS、86 FPS、+10.3%
このように、Dual RankのメモリはSingle Rankに比べてfpsが約8?11%向上することが分かります。
特に、CPU負荷が高いオープンワールドゲームやFPSゲームでは、Dual Rankの恩恵を受けやすいです。
Dual RankがSingle Rankよりも高速なのは、「バンク交互アクセス」が可能だからです。
メモリは「バンク(Bank)」と呼ばれる小さなメモリ単位にデータを分割して保存しています。
Dual Rankでは、2つのメモリグループを交互に使用できるため、スムーズなデータ転送が可能になります。
一方、Single Rankは1つのバンクしかないため、一定時間ごとに待機時間が発生しやすくなり、転送効率が落ちるのです。
一般的なPCゲームならば「32GB(16GB×2枚)かつDual Rank ×2」が適しているでしょうね。Quad Rank ×2の64GB構成までいくとクリエイター向けなので、オーバースペックかもしれません。
今後はメモリのランクも気にしてみよう
メモリのランク(Single Rank・Dual Rank・Quad Rank)は、ゲームのfpsや安定性に影響を与える重要な要素です。
特に、Dual Rankメモリを使用すると、fpsが約8~11%向上することが確認されており、CPU負荷の高いゲームでは効果が大きいです。
これからPCを組む方やメモリをアップグレードしたい方は、容量やクロックだけでなく、「ランク」にも注目して最適なメモリを選びましょう!