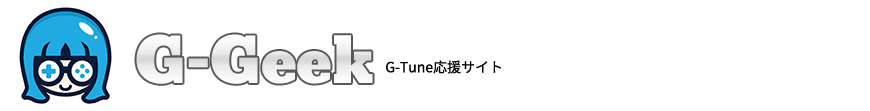使わなくなった32インチモニター、どのように処分すればよいか悩んだことはありませんか?PCゲーマーにとってモニターは「武器」とも言える重要な周辺機器ですが、買い替えの際には旧モニターの取り扱いにも注意が必要です。
特に32インチ以上の大型モデルは「粗大ゴミ」としての扱いや配送の手間など、一般的な不用品とは異なるルールが関係してきます。
そこで今回は、PCゲーマー向けに32インチモニターを安全かつ適切に処分するための方法と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。
「3Rマーク」があるモニターはメーカー回収が可能
モニター本体に「PCリサイクルマーク(3Rマーク)」が付いている場合、メーカーによる無償回収サービスが利用できます。
3Rマークは、2003年10月以降に販売された家庭用PCやディスプレイに付与されており、製造メーカーがリサイクル責任を負っている証です。
32インチクラスのモニターでも、このマークがあれば、製造元の回収申請フォームから簡単に申し込みが可能です。
梱包後、指定の伝票を貼るだけで、宅配業者が自宅まで引き取りに来てくれます。
メリット
・回収費用が無料
・正規ルートでの安全なリサイクル
・宅配回収なので持ち運び不要
デメリット
・3Rマークがない旧型モデルは対象外
・メーカー手続きがやや煩雑
自治体の粗大ごみ回収を利用する
3Rマークがない場合や、すぐに処分したい場合には、自治体の粗大ごみ回収に依頼する方法も検討しましょう。32インチモニターは多くの自治体で「粗大ごみ」に分類され、事前予約のうえ、収集日までに指定場所に出す必要があります。費用はおおむね300~800円程度の回収券を購入するケースが一般的です。
注意点として、CRT(ブラウン管)モニターなど古いタイプは回収対象外としている自治体もあるため、ディスプレイの種類を確認しておく必要があります。
メリット
・比較的手軽に依頼可能
・費用が安価で明瞭
デメリット
・収集まで日数がかかる
・玄関先までの搬出が必要
・技術的な安全処理が不明確な場合もある
リネットジャパンなどの認定事業者に依頼する
環境省と経済産業省が認定する「小型家電リサイクル法」対応の事業者を利用する方法もあります。中でも「リネットジャパン」は全国の自治体と提携しており、PCやディスプレイの宅配回収を手がけています。32インチモニターも対象で、1箱まで無料回収が可能(条件あり)です。
Web申し込みで回収キットを取り寄せ、梱包して送付するだけで、環境基準に沿ったリサイクルが行われます。
メリット
・回収申し込みがオンラインで完結
・条件を満たせば無料回収も可能
・技術的に高度な分別処理がなされる
デメリット
・サイズや重量に上限がある(幅・高さ・奥行き合計140cm以内)
・回収対象にならないモニターもある
迷わず処分するための最終チェックポイント
32インチのモニターはサイズが大きく、処分にも計画性が求められます。PCゲーマーにとっては新しい機材導入の妨げになるだけでなく、保管にもスペースを取る厄介な存在になりがちです。
適切な処分方法を選べば、法的リスクや環境負荷を回避できるだけでなく、技術的にも安全なリサイクルにつながります。3Rマークがあるならメーカー回収、ない場合は自治体回収や認定業者の利用といった選択肢を理解し、自分に合った処分方法を選ぶことが重要です。
次のモニター環境を気持ちよく迎えるためにも、ぜひこの記事の内容を参考にしてみてください。