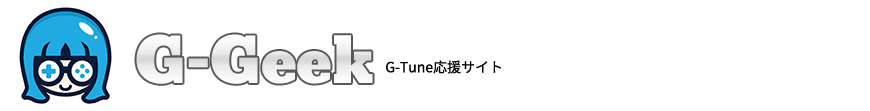ゲーミングPCを売却する場合、いくつかの方法があります。よく使われるのはオークションやフリマですが、その他にもショップやリサイクルショップなどさまざまな売却方法がありますよね。
今回は、こうした売却方法によってどれくらい価格が異なるのかをまとめてみたいと思います。
ヤフオクやメルカリなどは大体6割程度
まず、最もメジャーであろう売却方法である「ネットオークション」や「フリマ」ですが、だいたい新品価格の6割程度であることが多いですね。
最も、購入してからの年数やCPU・グラボの世代にもよりますが、私の感覚では「購入後3~5年」のものが6割程度で売れていると認識しています。
例えば、新品価格20万であれば12万円程度です。ただし、大幅な性能向上があった世代(Intelならば第7→8世代や第11→12世代など)の場合は、安くなってしまう可能性も否定できません。
これは、最新世代の下位グレードと比較されるためです。特にコア数やスレッド数が大幅に伸びたあとに旧世代のPCを売却すると、半額程度になってしまうこともあります。
とはいえ、最近のゲーミングPCはグラボさえそこそこであればそれなりに遊べてしまうので、出品時の写真や説明さえしっかりしておけば不当に安い価格にはならないでしょう。
専門ショップの買取は4~5割程度
次の候補としてはPCパーツを専門的に扱う専門店への売却です。こちらもグレードによりますが、おおよそ新品時の4~5割が相場ではないかと思います。
店側は買取価格に1~2割の利益を乗せるので、実際に売られる価格はヤフオクやメルカリと大差なくなるわけですね。
ヤフオクやメルカリよりも手軽に売却できて、出品や発想の手間もないことから、近くに店舗がありさえすれば最も素早く換金できる方法といえます。
また、2021年あたりのように半導体不足で高騰が起こっている場合は、新品購入時よりも高く売却できる可能性もあります。
リサイクルショップは3割を切ることも
最も安い買取価格になってしまうのが、一般的なリサイクルショップチェーンですね。ひどい場合は新品価格の3割を切ってしまいます。
最も、家電量販店の下取り(一律2000円など)に比べると高いのですが、それでも上記2つの方法に比べるとかなり安いです。
一般的なリサイクルショップはPCパーツの専門店と客層が異なるため、ゲーミングPCがあまり売れない(回転率が悪い)ことが原因なのかもしれません。
ちなみに私は、じゃんぱらなどで5000円の値がついたモニターを試しに持ち込んだところ、0円を提示されたことがあります。やはり専門店の査定とは差があるようですね。
パーツにばらして売るという手段も
もし査定価格に納得いかない場合は、CPUやグラボ、メモリなど主要なパーツだけを売却して、あとは保管しておくという手もあります。
主要パーツは後々買い足して、安く新しいPCを作る時のために取っておくわけですね。CPU・グラボ・メモリ・マザーボード以外は、数年経過しても性能がそこまで変わりませんから、売ってしまうよりはお得かもしれません。
実際に私の友人は、上記4つのパーツ以外を10年近く使いまわしています。さすがに電源はそろそろ交換のようですが、サブマシンなので稼働時間が少なく、主要パーツ以外はほとんど劣化がないようです。