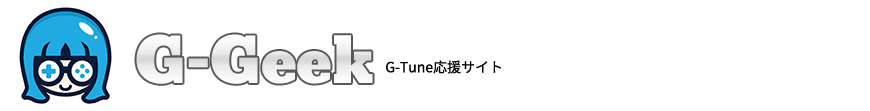RTX4090が登場し、性能もさることながら「巨大さ」が話題になっています。なんと前世代のハイエンドであったRTX3090比で、体積が1.5倍以上にもなっているからです。
今後、この傾向が続けば、空冷では冷却が追い付かずに簡易水冷が必須になるのかもしれません。果たして空冷は絶滅をまぬがれるのでしょうか。
RTX4090は空冷で冷却できるのか?
2022年10月に発売された「ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 Trinity OC」のカード寸法を見て驚いた方も多いと思います。
私は性能よりもまず、その大きさに目を奪われました。カード寸法は、356.1mm (L)x 150.1mm(W) x 71.4(H) mmとなっていて、長さ35センチを突破。
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Trinityの寸法が約317.8×120.7×58mmであったため、長さは約4センチも増大しています。
体積ベースでいうと、3090比の約1.7倍。この巨大な熱源には3連ファンが装着されているものの、ファンから排出された熱気を空冷で流し続けるのは厳しいと感じます。
そこでピンときたのが簡易水冷の存在。RTX40シリーズからは、本格的に簡易水冷が王道になっていくのかもしれないと感じました。
なぜなら、RTX4090の簡易水冷モデルを見ると、空冷モデルに比べてかなりコンパクトになっているからです。
GIGABYTEから出ているRTX 4090 搭載 簡易水冷グラフィックボード「GV-N4090AORUSX W-24GD」のカード寸法は、238 x 141 x 40 mm。前述の空冷モデルと比較すると…
・RTX4090空冷(3連ファン)…356.1mm (L)x 150.1mm(W) x 71.4(H) mm
・RTX4090簡易水冷…238mm(L) x 141mm(W) x 40 mm(H)
幅以外はかなり数値が小さくなっていますよね。長さは12センチ、高さは3センチも小さくなっています。これならばちょっと大きめのミドルレンジグラボです。
要は、消費電力と発熱の増加によって、空冷グラボに占めるファンの体積が大きくなりすぎているわけですね。また、空冷で排出された熱を処理するためには、PCケースにも相応の冷却能力が求められます。
しかし、この巨大な熱源を冷やすだけの能力が、果たして今のPCケースに備わっているかと言われれば疑問が残ります。
グラボが巨大になるほど存在感を増す簡易水冷
4090に限ったことではないのですが、グラボが巨大になるほど簡易水冷はメリットが大きくなると思います。
まず、グラボ本体の半分以上を占める巨大なファンが無くなることで、スペース的な余剰が生まれますよね。長さが10センチ以上も変われば、PCケースの大きさはミドルタワーからmicro ATXサイズに落とすことができます。
簡易水冷もラジエーターファンの設置場所が必要ですが、これは向きを変えられますし、最近のPCケースはラジエーターファンの設置場所もしっかり確保しています。
逆に空冷を前提に考えると、巨大なグラボを設置するためだけに巨大なPCケースを買わねばなりません。また、前面に大型ファンは2基以上、かつ底面と天板にも15センチファンが欲しいですね。
PCIeスロット部分にまで強力なエアフローを発生させるには、PCケース前面のファンからしっかりと勢いのある風が当てる必要があります。つまり、全体的にかなり騒音が出るでしょうね。
そして何といっても、4スロット占有という非常に非効率な空冷ファンの大きさが頭を悩ませます。4スロット占有となれば、PCIeスロット部分はすべてグラボだけで埋まりますし、ファンとサイドパネルのクリアランスもかなり厳しくなってきますよね。
エアフローはスペースが確保できないと効率が落ちますから、4スロット占有の空冷モデルを冷やすのはますます難しくなります。
個人的な予想ですが、RTX50シリーズや60シリーズが登場するころには、ハイエンドグラボ搭載のゲーミングPCは簡易水冷が前提になるのかもしれません。
また、空冷はミドルレンジ以下専用の冷却システムに落ち着つくのかもしれないですね。
このページだけの特別価格!シークレットモデル!
G-Tuneのシークレットモデルが文字通り密かに販売されています。G-Tuneで販売されているゲーミングPCよりもとても安いモデルがあります。いつまで残っているかわからないので今すぐチェックすべし!