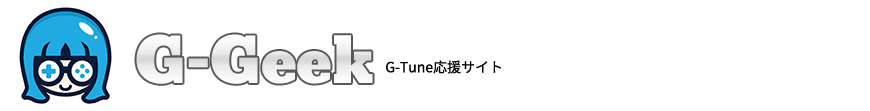多くのネットゲームでは、サービス開始直後は賑わっていたのに、数か月後には「過疎った」と感じる声が目立つことがあります。
しかし、その現象には実は単純な理由だけではなく、ゲーム特有の構造的な背景が存在します。
本記事では、なぜ大半のネトゲがすぐに過疎るように見えるのか、そのメカニズムについて整理していきます。
そもそも初期マップに集中する黎明期が特殊である
ネットゲームがサービスを開始した直後は、すべてのプレイヤーがほぼ同じ進行度でスタートします。
初心者向けの初期マップに大量のプレイヤーが集まり、どこへ行っても人の姿が見える状態ですよね。まずこの状態が特殊です。
初期マップにプレイヤーが集中している黎明期こそが、ネットゲームにおいて最も「賑わっている」と感じやすい時期であり、多くの人はこの時のイメージを基本とします。
しかし、これは一時的な現象であり、長く続くものではありません。
プレイヤーが成長すると居場所は分散する
プレイヤーはゲームを進めるにつれて、レベルが上がり、行ける場所や挑戦できるコンテンツが増えていきます。
当然、初心者エリアに留まる必要がなくなり、それぞれが自分の進行度に合わせたマップやダンジョンへ移動していきますよね。
この「成長による自然な分散」が、初期マップで感じた賑わいを薄れさせ、過疎感を覚える一因になるわけです。
コンテンツとゲーム進行度の多様化で分散する
現代のネットゲームは、単にレベル上げをするだけではありません。
PvP、ハウジング、クラフト、レイドなど、プレイヤーが選ぶ遊び方は多様化しています。
また、メインストーリーを進める人もいれば、サブクエストに没頭する人もおり、プレイスタイルが細かく分かれていきます。
このコンテンツの多様化がさらにプレイヤーの行動範囲を広げ、それぞれ異なるエリアやインスタンスに散らばる結果を生みます。
結果として同じマップに留まる人が減り、「人がいない」と錯覚しやすくなってしまうのです。
過疎っているように見えるゲームの特徴
ということで、私なりに「過疎っているように見えやすいゲームの特徴」をまとめてみました。
フィールドが広い
まずこれですよね。フィールドが広くマップの種類が多いと、どうしても過疎って見えやすくなります。
大規模なMMO RPGに多いのですが、ゲーム開始から時間がたつほどに、プレイヤーは活動時間帯もレベルもバラバラになっていくので、各マップに散らばります。
さらにアップデートでマップが追加されていくと、どんどん1マップあたりの人口は薄まっていき、さらに過疎感が強まると。
こうした「疑似的な過疎感」を防ぐかのように、広大なマップを作らないゲームも増えました。人口密度を意図的に高めることで、賑わいを演出するわけですね。
MOコンテンツが豊富
近年はMMOよりもMO(少人数の同時参加型)なコンテンツが人気です。バトロワ系もそうですし、モンハンなんかもいわゆるMOに属します。
しかし、MO的なコンテンツが増えていくと、プレイヤーは自分が好きなコンテンツに時間を割くようになり、人口が分散します。
さらにMOタイプのコンテンツはインスタンスとして提供されるので、参加中は一般のフィールドやマップにいません。
したがって、MOコンテンツに集中するプレイヤーが多ければ多いほど、過疎感が出てしまいます。実際には熱心なプレイヤーが多いのですけどね。
ソロコンテンツが多い
こちらも重要ですね。近年は無駄なコミュニケーションを避けて快適に遊べる「ソロ指向」なコンテンツが増えました。
しかしソロで遊べてしまうということは、他者を必要とせず、プレイヤー間のつながりは希薄になります。
実際にはプレイヤーが多くても、自分の感覚としては「つながり」がないので過疎と感じてしまいやすいのです。
良ゲーほど過疎っているように見える
ここで挙げた特徴は、実は「良ゲー」と呼ばれるタイトルの特徴でもあります。つまり、良質なゲームほど過疎感が出やすいのです。
重要なのは、「目の前のマップに人が少ない」という印象だけで過疎を判断しないということでしょうね。
プレイヤーたちは今もどこかでアクティブに活動しているかもしれませんし、別のサーバーやインスタンスにいる可能性もあります。
また、時間帯やコンテンツの開催状況によって、人の集まり方は大きく変わります。
単一のエリアを見て「過疎った」と結論づけるのではなく、ゲーム全体の人口推移やゲーム外のコミュニティ(DiscordやSNSなど)もチェックしたいですね。
このページだけの特別価格!シークレットモデル!
G-Tuneのシークレットモデルが文字通り密かに販売されています。G-Tuneで販売されているゲーミングPCよりもとても安いモデルがあります。いつまで残っているかわからないので今すぐチェックすべし!